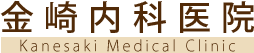2025/11/05
すっかり涼しくなりました。夏が暑すぎたので、寒い、とすら感じるくらいです。近年は秋が短くなっているとも言われますが個人的には10月からはしっかり秋になっていると思っています。貴重な時期ですので外に出て季節を満喫する機会を増やしたいところです。運動不足も今は寒さや暑さなどの気候のせいにはできませんね。
<かぜ情報>
10月末の時点ではいよいよ始まったな、と思うくらいには増えてきました。インフルエンザウイルスが大好きな低温と乾燥がすすむとさらに本格的な流行となるのかもしれません。新型コロナの流行は落ち着いています。それでも検査をすると陽性になる方が時々いらっしゃいます。新型コロナは従来から存在する「風邪コロナ」の一つに移行した印象です。それでもご高齢の方や肺に持病がある方が感染すると呼吸状態が悪化する場合があります。咳が長引くことで受診される方も増えています。発熱がないわりに激しい咳が続くケースでは検査してみると百日咳であったというケースもまだみられます。かぜにアレルギー症状が重なることで咳が長引くケースもあります。
<インフルエンザワクチン接種の開始>
ワクチンの供給に今のところ問題は起きていないので希望しても受けられないということはならないと思います。当院に慢性疾患などで定期的に受診されている方には定期受診の日に希望されれば予約なしでも接種をいたします。これも例年と変わらない体制です。昨年から、鼻に噴霧するタイプのインフルエンザワクチンが使えることになりました。対象年齢は2歳~19歳です。接種の予約を希望される方も徐々に増えてきています。注射タイプと違って1回打ちで済みますし(注射タイプは13歳以下では2回打ちが推奨されています)、痛みもありません。ただし生ワクチンですので接種後に発熱する場合がありますし、鼻かぜのような症状がでるときもあります。
<糖尿病コーナー>
以前も触れましたが、糖尿病という病名を変えようという動きが糖尿病協会(糖尿病学会ではありません)などを中心に続いています。新しい名称の候補となっているのが「ダイアベティス」です。糖尿病は英語で「diabetes mellites(ダイアベテス メリタス)」と言いますので要するに海外と同じにするということです。糖尿病の名称変更の一番の目的は糖尿病に対するスティグマ(偏見)をなくすためです。自己努力が足りない、だらしないから糖尿病になってしまうという間違ったイメージを払拭したい、そもそも糖尿病という名前自体が尿という言葉が入っていてイメージが悪い、というものです。個人的にはこの動きには疑問をもっています。糖尿病を自己責任にしてしまうというイメージを払拭することには大いに賛成です。私の著書にも書いてある通り、糖尿病には遺伝や社会環境、加齢など様々な因子が大きく影響しています。そして自己責任に帰すスティグマ(偏見)は治療の妨げになってしまいます。糖尿病改称運動を推進する人たちは糖尿病の名前自体のイメージがわるく、そのような名称で診断されると恥ずかしいと感じてしまい、治療と向きえなくなると言っています。そもそも糖尿病の本質は血糖値が高くなってしまうことであり、その結果として血液からあふれた糖が尿にでてしまうのです。例えば「高血糖病」ならより病態を正確に言い得ているかもしれません。「ダイアベティス」をその候補とした理由としては以下のようになります。まず、名前も海外と同じにしてグローバル化の流れに乗るということ。海外でと同じ病名になれば学術的な理解や議論がしやすくなるというのです。またより学術的なイメージをもつ病名をもつことで、本当の「病気」として向き合うことになり本人も周囲も本気になって治療に取り組める、あるいはサポートできるようになるということです。しかしダイアベティスが候補になってから既に数年になりますがその普及活動はあまりすすんでいないようです。そもそもいきなりダイアベティスにしても一般の人にはピンとこないでしょう。あなたは「ダイアベティス」という病気をもっていると言われてもピンと来ないでしょう。糖尿病内科がダイアベティス科になり、血糖値が高いと指摘されてもどこを受診していいかわからなくなるでしょう。そもそも尿とうい言葉が負のイメージをどのくらいもっているかは個人的には疑問です。尿は感染源としては血液よりずっと安全ですし厳密には汚いものではありません。昔は蜂に刺されたらおしっこをかけなさい、などとも言われていました。糖尿病という言葉は日本人が作りました。現在では中国と韓国でも使われています(中国では読み方が違いますがこの漢字が使われ、韓国は漢字表記をやめていますがハングル文字で「とうにょうびょう」に近い音を使っています)。だとすると糖尿病はダイアベティスのもう一つの国際表記とさえいます(10億人を超える中国の人口を考えると相当な規模になります)。これからむしろ胸を張って「糖尿病」といえる時代になって欲しいと思っています。
<院長の日記>
城好きな私にとって以前から気になるお城があります。駿府城です。徳川家康が江戸幕府を開いた後に大御所として晩年を過ごしたところです。現在の静岡市にあります。駿府の地は家康が今川氏に人質として預けられていた時に過ごした場所です。人質といってもそれほど酷い扱いを受けたわけではなく、むしろきちんとした教育も受けることができましたし、今川家の重臣の娘を妻に迎えました(後の築山殿)。ですから家康にとっては青春時代の思い出の地であったことでしょう。今川義元が桶狭間の戦いで織田信長に敗死した後、駿河の国は徳川氏と武田氏に分割され駿府は武田氏が支配しました。この時期、家康は浜松城を居城としました。武田氏が滅亡した後、駿河の国はついに家康が支配することとなり駿府を居城としました。やがて豊臣秀吉が天下を統一すると家康は関東への国替えを命じられ、江戸城に移りました。秀吉亡き後、関ヶ原の戦いで勝利して天下人となり江戸に幕府を開きましたがわずか2年で将軍職を秀忠に譲り、大御所となりました。再び駿府に戻り大掛かりな城普請を始めましたが天下人の隠居城ですから壮麗な城だったことは想像できます。明治以後は陸軍の土地となり残念ながら城も石垣も取り壊されてしまったのですが、最近になって発掘がすすみ、巨大な天守台があったことが分かりました。その大きさは圧倒的で当代随一のものであったようです。その天守台にどのような天守閣が建っていたかに興味のあるとろですがそれを確定的に伝える資料は少なく、なんとか様々な文献を総合して有力とされている天守閣の再現図があります。それはまさに異形の天守閣と言えるものです。天守閣は巨大な天守台と同じサイズではなく、天守台のほぼ中央に7層の天守閣がそびえ立ち、天守台の四隅に2重の隅櫓があり、それぞれが渡り廊下(多門櫓)で連結されています。天守台の中央にある天守閣とそれぞれの櫓の連結はなく(少なくとも外からは見えず)、これが他に例を見ない構造になっています。戦国時代から江戸時代初期に建造された天守閣の代表的な構造のひとつが「連立式」と呼ばれるもので天守閣も隅櫓と多門櫓の連結の一部(曲輪)を構成しています。代表的なのが姫路城です。この連立式は美しいと同時に機能的にも見えるので自然な造形美となっているのです。実際に防御力が高い形式とされています。私が大好きな和歌山城もこの構造です。城も「ミリタリーもの」ですが、戦艦や戦車、戦闘機などミリタリーもので自然な造形美としてカッコ良く見える条件の一つがこの「機能的な」要素があるところだと思います。美しさだけを追及するのであれば美術品になってしまいます。そして駿府城の天守にはこの機能的な要素がみられません。天下を完全に統一した家康にとってはむしろ天守の壮麗さで権威を見せつけることの方を重要視したのかもしれません。もはや城というよりは宮殿に近いでしょう(何かに似ているなと考えていたら中国の紫禁城の午門が思いあたりました)。さて、最後の将軍、徳川慶喜が江戸城を明け渡した後に徳川本家(宗家)は一時駿府に移り駿河藩となりました。やがて廃藩置県となり全国からお殿様(藩主)がいなくなったのですが徳川家は実質的には駿府で終わったのです。とても象徴的な出来事だとは思いませんでしょうか。ちなみに家康が築いた巨大な天守閣は江戸時代の初期に火災で焼失してしまい、その後は再建されませんでした。江戸城と同じです。江戸城の場合、戦(いくさ)のない時代にもはや必要ないとの判断だったそうですが、現在も皇居には巨大な天守台が残っています。私も実際に見ましたが不思議なもので巨大な天守台だけの方が想像力をかき立ててかえって異様な迫力があります。駿府城も天守閣自体は再建しなくてもいいのでせめて日本一の巨大な天守台が再建されることを望んでやみません。