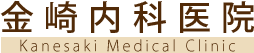2025/10/06
この紙面で何度も書いていますがやはり「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったものです。今年も実感しました。それでも平年よりまだ暑いようですが、気温が下がった落差は十分に感じます。それだけ暑くて長かったということです。最近は秋が短くなったと言われていますがこれが新しい形の秋と考えれば十分に楽しめるのではないでしょうか。
<かぜ情報>
今年は毎年夏に大流行する手足口病やヘルパンギーナは結局ほとんどみられませんでした。ただし、ウイルスによると考えられる肺炎が複数みられました。新型コロナもインフルエンザも検査では陰性で、発熱と咳が長引く場合にレントゲンを撮ってみると肺炎が見つかるというパターンなのですが、血液検査では炎症反応は軽微で抗生剤を使わなくても解熱してしまうといったものです。暑さで体力が落ちているのが関係しているのかなとも考えられました。
新型コロナはやや多いのですが増えているというよりは横ばいのようです。新型コロナももはや「波」と呼べるようなはっきりとした流行が観察されなくなってきている印象です。報道によると西日本からインフルエンザの流行が始まっているとのことで今年は流行シーズンが早くやってきそうです。この辺りでは10月の始めの時点ではまだ増えてきていないようですが警戒が必要のようです。
<発熱外来専用コンテナ診察室の運用開始のお知らせ>
8月から発熱外来専用のコンテナ診察室の運用を開始しています。新型コロナ感染拡大以降は駐車場の奥にプレハブを設置し、ここで発熱外来の診療をしておりました。しかしあくまで臨時のプレハブとしての運用であり、診療専用と言えるようなものではありませんでした。同じ場所に今回新たに設置した診療コンテナは感染症外来専用に開発された陰圧換気システムが設置しております。これにより2~3分で部屋の空気が全て入れ替わることになります。室内の空気の流れも一方向になります。受診者が室内の排気口の近くに座っていただくことになますが、これにより医療スタッフ、付き添い者、その後の受診者への感染がより防げるようになります。また、気密性と断熱性にも優れており喚起のために窓を開ける必要もないので、設置したエアコンにより夏は涼しく冬は暖かくなります。社会は既に新型コロナと共存できるようになりましたが、以前のように医療機関では感染症で受診される方と必要な方とそうではない方を同じ部屋であるいは隣同士で待ち合室にいていただくようにすることは今後もできないと判断し今回の設置となりました。この点はもうコロナ前には戻らないと思います。
<インフルエンザワクチン接種の開始>
10月からインフルエンザワクチンの接種を開始いたします。9月末から予約の受付も始めています。今年もワクチンの供給に今のところ問題は起きていないので希望しても受けられないということはならないと思います。当院に慢性疾患などで定期的に受診されている方には定期受診の日に希望されれば予約なしでも接種をいたします。これも例年と変わらない体制です。
<糖尿病コーナー>
「国宝」という映画を観ました(この先ネタバレにご注意)。公開からしばらく経っていますが、9月の末に映画館で観たときもほぼ満席でした。この作品は歌舞伎役者を題材にしています。映像美が見事で、俳優たちが演じる歌舞伎の場面も非常に印象的でした。私は歌舞伎の専門家ではありませんが、それでも素人の目から見ても十分に見応えがありました。映画のテーマとしては、芸事の厳しさや「世襲なのか、それとも実力なのか」といった問題が描かれています。その中で特に印象的だったのは、糖尿病がストーリーの重要な背景として描かれていたことです。劇中では、父が視力障害を抱え、息子は足の壊疽により切断を余儀なくされるという重い現実が描かれます。しかも、芸の継承とともに糖尿病も遺伝していく——この二重の「継承」の構図が非常に巧みに物語に組み込まれており、よくできた設定だと感じました。以前から繰り返し述べているように、2型糖尿病の発症には遺伝的な要因が大きく関与しています。同じ生活習慣でも親が糖尿病である場合、そうでない人よりも発症しやすくなるのです。これは本人の努力だけではどうにもならない部分です。映画の舞台は1970年から1990年頃で、当時は現在のように効果的な薬がまだ少なく、きちんと通院していても、失明や足の壊疽といった合併症が起こることは珍しくありませんでした。映画の中では通院治療の場面は描かれず、むしろ病気を放置していたように見受けられます。もちろん、いくら良い薬があっても治療を受けず放置すれば合併症が発症・進行してしまうのは今も昔も変わりません。しかし、全体として糖尿病による下肢切断や失明は現代では確実に減少しています。この点については、私の著作でもデータを示して紹介していますので、興味のある方はぜひお読みください。糖尿病の治療は今もなお急速に進歩しており、たとえ糖尿病の素因を受け継いだとしても、親の世代よりも子の世代の方が、より有効な治療を受けられる時代になっています。これからさらに時代が進めば糖尿病による合併症がストーリーの中心に描かれることは現代劇としてはもう見られなくなるかもしれません。おそらく、そうした描写は昭和を舞台にした「時代劇」の中にのみ残っていくことでしょう。
<院長の日記>
トランプが大統領に再就任してから半年が経ちました。2期目に入ってむしろ「トランプ節」にさらに磨きがかかり、世界が翻弄されているようです。トランプの考えていることが理解できない、さらにはトランプを再び大統領に選んだアメリカ国民の気持ちが理解できない——そう感じている人も多いのではないでしょうか。では、このような「トランプ現象」は今回に限った異例の出来事なのでしょうか。実は、アメリカの建国以来の歴史や建国の理念をたどると、決してそうではなく、むしろ必然とも言えることがわかります。実際、トランプのようなタイプの大統領は過去にもいました。代表的なのが、第7代大統領アンドリュー・ジャクソンです。建国間もない時期の大統領で、時代背景は現在とは大きく異なりますが、それでも多くの点でトランプと似ています。ジャクソンは西部の開拓地出身でした(それ以前の大統領は建国の地である東海岸出身者ばかりでした)。若いころは勉強が苦手で、本もほとんど読まなかったといわれています。アメリカ独立戦争に従軍して武功を挙げましたが、もともと戦いが大好きで、個人的な決闘も何度も行い、亡くなるまで体内に銃弾が残っていたそうです。また、筋金入りの人種差別主義者で、他人の妻と結婚(重婚)してしまったとも伝えられています。なんとか法律家になり、うまく事業をすすめて大きな富を築いたジャクソンは大統領選挙に出馬します。対立候補はアダムス。ジャクソンとは対照的で、父も大統領、自身もハーバード大学出身という超エリートでした。この初戦ではジャクソンは敗れますが、4年後に再びアダムス(当時は現職大統領)に挑戦します。このときの選挙は、激しいネガティブキャンペーン合戦となりました。ジャクソンは「前回の選挙は不正だった」と主張し、アダムスは「ジャクソンの妻は重婚罪を犯している」と中傷します。結果、今度はジャクソンが勝利を収めました。アダムスのリベラル的な政策が国民の支持を失ったとも言われています。アダムスの掲げていたリベラル政策とは、たとえば国立の図書館や天文台の設立、奴隷制度の禁止、他国との協調外交などです。一方でジャクソンは大統領就任後、それまでの官僚を解雇して自らの支持者に入れ替えるという政策(猟官制度)を実施しました。彼はまさに「アメリカンドリーム」を体現した人物だったのです。いかがでしょうか。トランプ大統領に似ていると思いませんか。アメリカにはもともと、知識層や富裕層(いわゆるエスタブリッシュメント)が権力を握ることを嫌う国民性があります。「自分たちの思想や信条は、他人に支配されたり縛られたりするものではない」という強い信念があるのです。そもそもアメリカ建国の原点は、宗教的迫害から逃れてきた人々にあります。彼らは国家建設を目的にしたのではなく、「自らの信仰を貫くための移住」を選び、その代わりに「他者の信仰も尊重する」という理念を掲げました。一方で、アメリカは新しい国であるため、他国のように伝統的な価値観が国の拠り所として根付いていません。その結果、「理性」を重んじ、それを世界に普遍化しようとする思想が育ちやすくなったようです。この2つの価値観の間での権力交代が、アメリカの歴史そのものといえます。トランプの前任者であるオバマ大統領は、ハーバード大出身のアフリカ系移民の子孫であり、演説も巧みでまさにリベラルを象徴する人物でした。このような極端な振れ幅こそがアメリカであり、同時に他国にとっては理解しがたいものなのかもしれません。