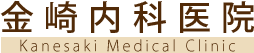2025/07/04
梅雨らしい天気が少なくあっという間に夏に突入のようです。近年は夏の暑さが異常なので四季がくずれていて、1年を「夏とそれ以外の時期」、といった感覚でとらえるようになってきました。今年は夏の始まりが早いのでますますそのような季節感となりそうです。
<かぜ情報>
かぜ症状で受診される方が増えてきています。新型コロナも6月末の時点でわずかながら増えてきています。やはり夏にはまた感染の波が来るのかもしれません。なぜか毎年夏にピークが来ています。
<夏季休診のお知らせ>
8月15日から8月20日までは休診とさせていただきます。例年よりも5日程、後にずれていますのでご留意くださいませ。
<伊奈町特定検診の開始について>
6月18日から毎年恒例の伊奈町の特定検診が始まっています。伊奈町在住の国民健康保険証か後期高齢者証をお持ちの方が対象です(オプション検査となっている胸部レントゲンや大腸がん検診:便潜血などは社会保険に加入の方でも受けられます)。対象者には伊奈町から案内(受診券)が届きます。当院でも接種券が届いた方から予約を受け付けます。今年は期間がやや短くなり10月末までとなります。毎年9月以降は予約がとりにくくなる可能性もありますので早めの受診をおすすめします。ちなみに町の6月号の広報で検診受診促進の特集でインタビューに答えるという形で取り組みに協力させていただきました。
<糖尿病コーナー>
前号の続きで今回は尿蛋白(タンパク)についてです。もともと蛋白は尿には微量ながら含まれますがあくまでも微量のため簡易的な尿検査(試験紙などを使ったもの)では基本的には(-)(:マイナス・陰性)と判定されます。一方で、尿から蛋白が検出された場合には何らかの腎臓疾患の可能性を考慮する必要があります。腎臓は血液を「ろ過」しており、ろ過後の水分と微量物質が尿として体の外に排出されます。ろ過膜の網目は細かく、蛋白の分子量よりも網目の穴が小さいため基本的には蛋白は尿には漏れ出てきません。この腎臓の中で血液のろ過を行うところを糸球体と言います。糸球体は片方の腎臓に100万個あります。腎臓になんらかの疾患が存在し、特に糸球体に障害が起きると、ろ過膜が壊れてしまいます。すると網目がやぶれて穴が大きくなってしまうので蛋白が血液から尿に漏れ出てきてきます。これによって尿蛋白が検出されるのです。慢性腎臓病はゆっくり病状が進行しますが多くの場合、血液検査で腎臓の働きが落ちてくるのが検出されるより先に尿蛋白が検出されるようになります。従って、尿蛋白は腎臓の疾患をより早く見つけるための指標にもなるのです。また尿蛋白はその量の多さが重要です。尿蛋白が多いほど腎臓の疾患は速く進行します。
このように尿蛋白は腎臓の病気を早く見つける指標であるとともに腎臓の疾患の進行の速さの予測因子としても有用です。尿蛋白が検出される慢性腎臓病で最も多いのが糖尿病による腎臓病です。糖尿病性腎臓病または糖尿病関連腎臓病ともいわれます。簡易的な尿検査で(+)(プラスまたは陽性)となった場合にはさらに厳密にその程度を調べることになります。尿はその量や濃さが大きく変化します。濃い尿ではタンパクを含め様々な尿に含まれる成分が多めに検出されてしまいます。特に外来診療で実施させていただている試験紙を用いた検尿では尿の濃さの影響を受けてしまいます。そこで外部の検査会社に依頼をして尿の濃さの影響を取り除いた正確な量を調べてもらうことが大切です。糖尿病の場合は蛋白の一種であるアルブミンを測定しその値によって糖尿病性腎臓病の進行程度を把握することができます。尿アルブミンによって腎臓合併症程度(病期)を分類分けできるのです。ちなみに尿アルブミンは尿タンパクの大部分を構成しているので、尿アルブミンが多いと「尿アルブミン=(イコール)尿蛋白」といって間違いないでしょう。
当院では糖尿病で受診された方の毎回の検尿で尿蛋白も検査していますがこれは糖尿病に関連した腎疾患を把握するためのものなのです。ちなみに尿蛋白は直近の血糖の影響はほとんど受けません。
<院長の日記>
今や夫婦共働きが当たり前の時代になりました。子どもは保育園に預けられるか祖父母などが面倒をみることが多くなってきているようです。保育士さんや預かる祖父母も大変でしょうけど、子どもも親と離れて過ごすことになります。つまり親以外の人と過ごす時間が増える一方で親と過ごす時間が少なくなります。
私の場合、母が専業主婦でしたのでそのような経験をしたことがほとんどありませんでした。なんとなくそのように思っていました。ところが記憶を頑張ってたどってみると人生で2回だけそのような時期がありました。2人の弟の出産の時です。すぐ下の弟が生まれたのはアメリカにいたときです。私は父の仕事と留学の都合で2歳から5歳までの間アメリカに住んでいました。次弟は私の3歳下なので私が3歳の時に母がアメリカで出産したことになります。この時は母方の祖母がアメリカに来てくれました。と言ってもこのときの記憶はほとんどありません。なんとなくおばあちゃんが来てくれた、くらいの記憶しかないのですがかなり後、というか最近になって母が出産だったので来てくれたのだな、と気づきました。母方の祖母は外国にも慣れていたので来られたのだな、とも納得しました。母方の祖父は外務省に勤務していたことがあり、母とその姉(私の叔母)はラオスやレバノン(ベイルート)にしばらく滞在した経験があると聞いたことがあります。ちなみのその叔母はその縁で外交官と結婚しました。とにかく、異国の地アメリカで母が不在の間私はどう感じていたのか、と今になって考えてみますが結局覚えてないので大したことではなかったのだと思います。もっとも出産だけなので母が家にいないは数日だけだったのでしょう。
よりはっきり覚えているのは末弟の出産の時です。このときは私が日本に帰国して小学校に入学したばかり、しかも3歳くらいの弟もいます。さらに母は出産の前後にしばらく入院していたように記憶しています。未だに理由はよく聞いていないのでわからないのですがとにかく不在の期間が長かったと思います。なぜ長かったと感じたかというと、今度は父方の祖母がきてくれてしばらく一緒に過ごしたときのことを今でもよく覚えているからです。一緒にスーパーに買い物に行って夕食に食べたいものを聞かれたり、食べたいお菓子は何でも買ってくれたのをよく覚えています。生まれてくる弟の名前を一緒に予想したりもしていました。祖母は妙に自身たっぷりに名前を予想して(決めつけて?)いましたがそれは私と次弟の名前からそれぞれ一字とって組みあわせたものでした。実際に父がつけた末弟の名前は全然違っていましたが。
人間ほど子供の養育に時間と手間をかける生き物はいないと思います。そしてその養育に親だけが関わるというではなく、親族やコミュニティも参加していたのだと思います。戦後に核家族化して父親の給料が右肩上がりだった一時期は母親が専業主婦として「専ら」育児に関わっていたのかもしれません。しかしそのようなことの方がむしろ例外で子どもは常に親と一緒にいなくても育つもの、しかもそちらの方が健全なのかもしれません。親は仕事をしていることが前提でもちろん育休は取るべきときはとる、そして時期が過ぎたら社会(コミュニティ)で関わる、そのようなシステムが我が国では未熟であることは感じます。