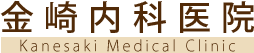2025/09/03
去年、一昨年と記録的な猛暑だったのを覚えています。記録的というものはそう簡単に続くものではありません。まさか、今年は去年ほどではないだろうと思っていました。ところが今年は40度越えも連発するなどさらに暑くなってしまいました。
診察の時に腕が日焼けをしている方をよくお見受けしますが対照的に真っ白な私の腕がまるで楽をしている証のようにみえて申し訳ないと思えてしまいます。
9月になっても暑さは続くようですがさすがにもうピークを過ぎたと思うようにしましょう。先が見えないとつらいばかりです。
<かぜ情報>
発熱外来の予約枠が埋まるほどではありませんが新型コロナは確実に増えています。
昨年夏に大流行した手足口病やヘルパンギーナも9月初めの時点でもまだほとんどみられません。
溶連菌、マイコプラズマ肺炎が時々みられます。
<発熱外来専用コンテナ診察室の運用開始のお知らせ>
8月から発熱外来専用のコンテナ診察室の運用を開始しました。
ご存知の方も多いと思いますが、新型コロナ感染拡大以降は駐車場の奥にプレハブを設置し、ここで発熱外来の診療をしておりました。しかしあくまで臨時のプレハブとしての運用であり、診療専用と言えるようなものではありませんでした。
同じ場所に今回新たに設置した診療コンテナは感染症外来専用に開発された陰圧換気システムが設置しております。これにより2~3分で部屋の空気が全て入れ替わることになります。室内の空気の流れも一方向になります。受診者が室内の排気口の近くに座っていただくことになますが、これにより医療スタッフ、付き添い者、その後の受診者への感染がより防げるようになります。
また、気密性と断熱性にも優れており喚起のために窓を開ける必要もないので、設置したエアコンにより夏は涼しく冬は暖かくなります。
社会は既に新型コロナと共存できるようになりましたが、以前のように医療機関では感染症で受診される方と必要な方とそうではない方を同じ部屋であるいは隣同士で待ち合室にいていただくようにすることは今後もできないと判断し今回の設置となりました。この点はもうコロナ前には戻らないと思います。
<糖尿病コーナー>
今回はジェネリック医薬品に関するお話です。処方される薬には「先発医薬品」と「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」があります。先発医薬品とは、最初に開発され、発売・処方される薬のことです。大手製薬メーカーが多額の費用と時間をかけて研究・開発し、特許(ライセンス)を取得して販売します。この特許の有効期間中は、他社が同じ成分の薬を製造・販売することはできません。
しかし、一定期間が経過して特許が切れると、他のメーカーも同じ有効成分の薬を製造・販売できるようになります。先発医薬品と違い、研究開発費がかからないため、後発医薬品はより安価に提供されます。この後発医薬品が「ジェネリック医薬品」です。
ジェネリック医薬品は安価なため、患者さん自身の薬剤費の自己負担額が減るだけでなく、健康保険で支払われる薬剤費も削減され、結果として国全体の医療費抑制にもつながります。ご存じのとおり、国の財政は厳しい状況にあり、医療費の削減は重要課題とされています。そのため、国や保険者(自治体や企業の健康保険組合など)がジェネリック医薬品の使用を推奨しています。
この方針は診療報酬制度にも反映されており、医療機関が処方箋に「ジェネリック医薬品を使ってもよい」と記載すると加算がついたり、薬局においてジェネリック薬の調剤割合に応じて報酬が変動するなど、さまざまなインセンティブが設けられています。
さらに、ジェネリック医薬品を自由に選べるようにするために「一般名処方」という制度があります。一般名とは、薬の化学的な成分名のことです。これに対して、先発医薬品メーカーがつける名前は「商品名」と呼ばれます。たとえば、アレルギー薬の「アレグラ」は商品名で、一般名は「フェキソフェナジン塩酸塩」です。診察室では「アレグラを出しておきますね」と言われても、処方箋には「フェキソフェナジン塩酸塩」と記載されます。これが一般名処方箋です。
一般名処方箋であっても、薬局で必ずジェネリック薬が渡されるわけではありません。多くの患者さんは薬代が安くなるためジェネリックを選びますが、逆にジェネリック医薬品に不安を感じ、先発医薬品を希望される方もいます。
こうした背景を踏まえ、昨年の診療報酬改定では「長期収載品の選定療養」という制度が導入されました。これは、医療上の必要性がある場合を除き、先発医薬品を希望したときには、ジェネリックとの差額の4分の1を自己負担するという仕組みです。
「長期収載品」とは、ジェネリック医薬品がすでに存在する先発医薬品のことです。また、医療上の必要性とは、ジェネリックでは副作用が出る、剤型が合わず服用できない、先発品にしかない効能で処方する必要がある、学会ガイドライン上先発が推奨されている、などが該当します。単に「ジェネリックが信用できない」という理由では対象外となり、自己負担が増えることになります。
なお、すべての長期収載品がこの制度の対象になるわけではなく、ジェネリック発売から5年以上経過したものなど、いくつかの基準があります。糖尿病治療薬では、SU薬、グリニド薬、チアゾリジン薬、α-グルコシダーゼ阻害薬、DPP-4阻害薬(一部)などが対象になっています。
過去には一部ジェネリックメーカーの不祥事が報道され、不安を感じる方もいるかもしれません。しかし現在では、ジェネリック医薬品は医療現場に不可欠な存在となり、大きなシェアを占めています。私自身も家族に処方する場合は基本的にジェネリックを選んでいます。風邪薬などでは、そもそも薬局に先発医薬品がほとんど置かれていないことも多いです。
これからの医療は、ますますコスト意識が求められる時代になっていくでしょう。
<院長の日記>
最近、海外のカーアクション映画をよく観ますが、そこでは多くの日本車が登場します。それどころか、主人公や敵役が乗っている車が日本車であることも非常に多いのです。
人気のカーアクション映画としてまず挙げられるのは「ワイルド・スピード」シリーズでしょう。長年人気のシリーズです。 シリーズ第1作では、主人公が最初に乗るのは三菱のエクリプスですが、中国系ギャングに壊され、その後はトヨタのスープラに乗り換えます。トラックを襲う強盗団が使う車はホンダのインテグラで、ギャングが乗るバイクはカワサキやホンダです。まるで日本車のプロモーション映画のようですが、その後のシリーズでも日本車は頻繁に登場します。
他にも「ベイビー・ドライバー」では主人公の愛車がスバルのインプレッサWRXですし、私の好きなフランス映画「TAXI」シリーズでも日本車が登場します。スピード狂のタクシードライバーが主人公のコメディタッチのカーアクション映画で、これもシリーズ化されました。主人公はプジョーに乗りますが、敵役は毎回変わります。第1作ではドイツの連続銀行強盗団がメルセデスに乗っていますが、「TAXI2」では敵が日本のテロリスト集団で、彼らの車は三菱のランサーエボリューション(通称ランエボ)です。
これほど日本車が映画に多く登場する理由はいくつか考えられますが、小さくて小回りが利き、カーアクション向きであること、そして高い走行性能が海外でも評価されていたことが大きいでしょう。日本のメーカーは乗用車や商用車だけでなく、スポーツカーも積極的に開発・販売してきました。こうした販売戦略が技術力の向上につながり、自動車大国アメリカでも認められたのでしょう。自動車を「乗る」「作る」「楽しむ」時代であり、社会全体にも余裕があった時代だったのかもしれません。かつてF1ではホンダが強さを誇り、ル・マン耐久レースではトヨタやマツダが優勝しました。
ところで先日、日産の「GT-R」が生産終了になるとの報道がありました。スカイラインをベースにした2000万円超のマニア垂涎のスポーツカーでしたが、開発コストの高騰が理由とのことです。日産の現状を考えると仕方ないのかもしれませんが、やはり寂しい気持ちになります。
現在は中国の電気自動車や韓国メーカーの車がシェアを拡大しており、日本車の海外シェアは減少傾向にあります。しかし、必ずしもかつて日本車が席巻したスポーツカーの市場には及んではいないようです。今は環境への配慮や価格競争が重視される時代であり、中国車が高い競争力を持つのも理解できます。
それでも、車には単なる道具以上のエモーショナルな要素があると私は思います。車はパートナーのような存在であり、愛着が湧くものです。これからは電気自動車の時代になると言われていますが、電気自動車にどこまで愛着を持てるのか、正直まだ想像がつきません。電気自動車が疾走するカーアクション映画やレースを思い描いても、あまりワクワクしないのです。車を楽しむ時代が終わりつつあるのかもしれませんが、日本車が「車の黄金時代」に確かな足跡を残したことは、記憶にとどめておくべきだと思います。