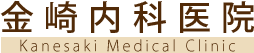2025/05/08
寒さもなくなり、花粉症も落ち着き、梅雨や暑さの前の束の間の貴重な時期です。今、外にでなければいつ出るのかと思ってしまいます。個人的には仕事もありますし休日の過ごし方も変わらないので特に日差しを浴びることが増えていませんが、人にはいつも薦めています。新緑を楽しみましょう、と言いたいところですがどちらかとう木々の葉ではなく雑草ばかり目につくこの頃です。
<かぜ情報>
少しずつ風邪症状で受診される方が増えています。4月から保育園に入学したばかりの1歳前後の小児のかぜ症状が目立っていますが毎年この時期は同様の傾向となります。一部の高校でインフルエンザが散発的にみられているようです。新型コロナはここ半年では最も少ない印象ですが、決してゼロではありません。
<糖尿病コーナー>
当院では4月後半よりHbA1cの院内での測定器の入れ替えを行いました。従来まで使用してきた機器の使用年数がかなり経過しておりメーカーでは既に製造中止になっていること、故障した場合の部品の供給も停止になっていること、そして何より故障のため修理に出していた測定器械の修理の目途が立たないこと、などが背景となり今回の新規の機器の導入となりました。HbA1cの測定方法は3つに大別されます。HPLC法、酵素法、および免疫法です。詳しい説明は専門的になってしまいますので省略しますが、当院では従来はHLPC法の測定器の小型タイプ(アダムス・ミニ)を2台使っていました。そしてそのうちの1台がこのたび故障となりました。今回新規導入したものも同じメーカーの同じ測定原理(HPLC法)のものです(HA8190-V)。検査室でご覧になればすぐ気づくと思いますがかなりの大きさの機器です。従来のものとの精度の差を数値で表すのは難しいですが、ある程度の規模の病院の検査室に置かれるレベルのもので当院のようなクリニックでは不釣り合いにも見えるからもしれませんが、糖尿病診療を専門としていることを改めて考慮にいれ、故障も含めてより信頼性の高いものを重視した結果今回の決断となりました。測定時間は従来のものよりは短く、いっぺんに複数の検査もできてしまいます。ただし申し訳ありませんが、検尿などその他の検査結果が出る時間は変わりありませんので従来とお待たせする時間はあまり変わりないかもしれません。また、検体(採取した血液)の取違いを防ぐため基本的には従来通り一人ずつの測定とさせていただく方針です。それでも従来のように2台の機器を併用するよりもむしろHbA1c自体の検査時間は短くなります(ちなみにもしもの時のためにももう一つの検査機器も常に使用できる体制は維持する方針です)。HPLC法はHbA1c測定の基準となる方法ですが、酵素法や免疫法もHPLCと精度などでの違いがない機器であれば、どの方法でも問題はないとされています。しかし、測定方法や施設間での測定値の違いはある程度想定され、同時に複数の検査法で測定しても全く同じにはならないことは起こります。例えばつい最近他院で受けた人間ドックでの数値と当院での測定が0.1-0.5%程度の違いがでることはあり得ます。日常診療でのHbA1cの測定の意義はどちらかというとその数値の「変化を」見ることの方が重要です(モニタリング)。同じ施設での同じ測定方法ではであればそれが可能となります。ただし、厳密な診断のために測定する場合には精度の高い検査法が必要となります。例えば、糖尿病の診断基準の一つにHbA1c 6.5%以上というものがあります。もし数か月前の他院での人間ドックでの測定値が6.3%を指摘されて受診された、などの場合にはより厳密な測定結果が求められます。そもそも推移をみるためではなく診断のためには基準をクリアした測定法(NGSP認証)でなければならないとされています。簡易型の測定器(POCT)は基本的には該当しません。当院でもこれまでは糖尿病かどうかの厳密な判断が求められた場合には静脈採血の上、外部の委託検査での測定としておりました。今回導入した機器はNGSP認証を受けたものですし静脈採血での検査にも対応していますので今後は診断にも使えることになります。
<院長の日記>
ペットなどの動物につける名前についてこんな話をきいたことがあります。国によっては鳥には人間と同じ名前をつけることがあるが、犬には人と同じ名前を付けることは決してない、というのです(日本では鳥にも人と同じ名前をつけることは少ないと思いますが日本語では人の名前は独特の響きを持つ言語だからでしょうか)。まず、犬については人と同じ名前をつけないというのは納得できるでしょう。今や猫とともにペットの代表的な動物ですが、昔から人に寄り添うように生きてきた動物です。もちろんかつては野生の犬もいたでしょうが、誰でも気軽に人に飼育できる対象として真っ先に挙げられる動物です。一方で飼育と言ってもウシやブタやヤギのような家畜ではありません。かといって人とは対等なパートナーという訳でもありません。どんなに可愛くても関係を一言で表すとすれば「従属」です。従属されている存在に人と同じ名前をつけるのはやはり抵抗を感じるでしょう。もし自分と同じ名前をつけられた犬をその飼い主が連呼しているのを聞いたらいい気分がしないでしょう。映画「男はつらいよ」でもいつのまにか寅さんが不在(いつもの放浪ですが)のときに家族が飼うことになったノラ犬に「トラ」と名前がつけてられているのを知った寅さんはやっぱり激怒していました(このシーンはお腹をかかえて笑えます)。「めぞん一刻」ではヒロインの響子さんが自分の亡き夫と同じ名前の惣一郎とつけていましたがそれは例外として・・・。前置きが長くなりましたが、話題は鳥の名前についてです。鳥には人と同じ名前をつけるということがあるというのを事実として、その理由を考えると鳥と人との興味深い関係が考察できます。これはフランスの哲学者レヴィ=ストロースの唱えた理論から話が始まります。彼は未開の部族の調査研究で業績をあげていきました。なかでもトーテムポール(トーテミズム)についての考察は有名です。トーテムポールには鳥が描かれていますし、さらには鳥の名前を自分たちの部族の名前にしているケースもとても多いのです。人は鳥を自分たちと同一のものと捉える(「融即」)思考をもつ(習性がある)との説が一時は有力でしたが、レヴィ=ストロースは鳥は融即ではなく「比喩」であるとの結論に達しました。いまはこれが定説です。鳥はイヌや家畜と違って自由に飛び回っている(ように見える)し、群れを作り、巣を作り、子を育てますし様々な形や色をしているので、人との対比がしやすい(というより対比しないではいられない)などの特徴から比喩として使われてきた、というのです。正確には隠喩や換喩と言います。かつては王家や国でも紋章に取り入れられたのは鳥が圧倒的に多いです。ハプスブルク家の紋章は双頭の鷲です(ちなみに鷲と鷹は大人気なのであちこちでかぶってしまいました)。現在、何かとお騒がせのアメリカもハクトウワシが紋章に使われています。ずっと非公式な位置づけでしたがバイデン政権のときに正式に国章となりました。実はほとんどの国で「国鳥」が定められています。ちなみに日本の国鳥はキジです。私も最近までは知りませんでした。聞かれたらトキと答えたくなるのは私だけでしょうか。そういえばプロ野球の球団で鳥の名前を使っているのが3つもあります。鷹(イーグルス)と鷲(ホークス)と燕(スワローズ)です。自然を分類したがるというのも人の習性でこれにより世界が豊かに見えるようになり、ふと鳥をみてみたときにもつい分類してしまった挙句に比喩の対象にしてしまうとうこの話、私は大変興味深いと思います。ちなみに先ほどの寅さん激怒のきっかけの犬ですが、お寺を「ウロウロしていた」のを近所の人たちが誰ともなく自然に「トラ」と呼ぶにようになったのだそうです。そして「トラ」なんだから、との理由で寅さんの家族に押し付けられ、そこに寅さんが旅から返ってきてしまったとのことでした。この場合、寅さんを犬の比喩にして表現したということになります。鳥だったら寅さんは怒らなかったでしょうか。